
Yum@は東工大合格したとき、どんな化学の参考書使っていたの??

じゃあ今回は、僕が実際に東工大に現役合格したときの化学の参考書ルートを公開しようと思うよ!!
よろしくね!
こんにちは、東京工業大学機械系3年のYum@です。
詳しい自己紹介はこちらです。
僕は受験期の冠模試はすべてE判定でしたが、2022年の入試で現役逆転合格しました。
気になりませんか??、東工大に逆転現役合格した参考書ルート。
良き参考書とその使い方を知り、学んでいけば、まだ間に合います!!
合格している自分を想像しながら、読み進めて見てください!!
-この記事の内容-
・実際に東工大に合格した化学の参考書ルートとその使い方
・化学の勉強方針
・高校化学の考え方
実際の化学の勉強方針
僕の化学の環境
僕の化学は、参考書中心で、スタディサプリと併用して学習するという方針でやっていました。
中でも、あとで紹介する「福間の無機化学の講義」と「鎌田の有機化学」をバイブルとしてこれに、理論化学で必要な暗記事項をメモで挟んで持ってました。
正直化学は数学や物理と比べて難しい問題がそんなに出されないので、勉強の優先度としては東工大の4教科の中で一番低いです。
化学は暗記さえできれば、一番イージーな科目です。
でも駿台の化学特講では、難しい問題が体系化することで楽に解けることを知り、「もっと早く知っとけばよかった」と思いましたが、化学に割ける時間を考えるとこれでよかった感じもします。

お金とか時間に余裕があるんだったら、予備校で体系的に学ぶのが安心だとは思うよ。
でも志望校が難関大(東京工、早慶、医学部)じゃなかったらスタサプで十分だと思うよ!!
化学は正直知っているか知らないかのゲームなので、模試で得点を稼ぎたいのであれば、予習をバリバリやるのをお勧めします。
化学の考え方
化学で重要なこと
・公式の背景を理解する
・暗記で多少何とかなる科目
・計算力が勝敗を分ける
・自分一人で考え抜く
・定石を覚える
・難しい問題は連想ゲーム
化学の考え方は基本的に数学と同じですが、気を付けてほしいことがあります。
まず、化学の諸現象は電子が常に関与しているということを理解しましょう。
理論化学でいう酸・塩基反応、酸化還元反応や有機化学でいう求核反応、求電子反応、ラジカル反応などほとんどすべての化学現象は電子が関係しています。
また、教科書はしっかり目を通してほしいですが、教科書を軸にはしないほうがいいです。
化学の教科書はとりあえずページ数が多く、情報を簡潔に書いていません。
しかし、すべての入試の問題は教科書を出題範囲として出します。
すなわち化学物質などの用語を問う問題は、すべて教科書に載っているものなのです。

東工大化学の毎年出る問題である正誤問題には本当にマニアックな用語も出ますが、すべて教科書に載っているのです。
東工大の過去問や実践問題を解いていく中で「ルビーやサファイアは酸化アルミニウムを主成分とする結晶であり、ルビーにはクロム、サファイアには鉄とチタンが含まれている」みたいな正誤問題があり、さすがに教科書にこんなこと載ってないと思っていたら、教科書のページの注に書かれてました。
東工大の正誤問題を完璧にやるなら、教科書にある知識をすべて覚えることをしたほうがいいです。
周期表は頭に入れときましょう。
周期表は縦で覚えると、使えるようになります。
僕はYoutubeにあった「下ネタで覚える周期表」的なやつで頭に入れました。
下ネタだとかなり苦戦していた周期表がすぐに覚えられました笑笑

化学の計算は数値計算が多く、方程式計算などは数学や物理と比べるとかなり少ないですが、計算力は必須です。
特に理論化学はかなり計算を要します。
でも計算をうまく処理する方法を教えてもらう機会って全く無いですよね??
そして、あとは解くだけなのに、計算が煩雑になって解けないのは、すごくもったいないです!!
そして、もったいないでは済まされない!!
それを解決してくれるのは駿台文庫の「数学の計算革命」という参考書です!
これを一通りやったとき、あなたの計算が格段に正確に早くなることでしょう!!
その他の三つの重要事項は、数学と同じです。
僕が過去に書いた数学の勉強法に関する記事に詳しく書いてあります。
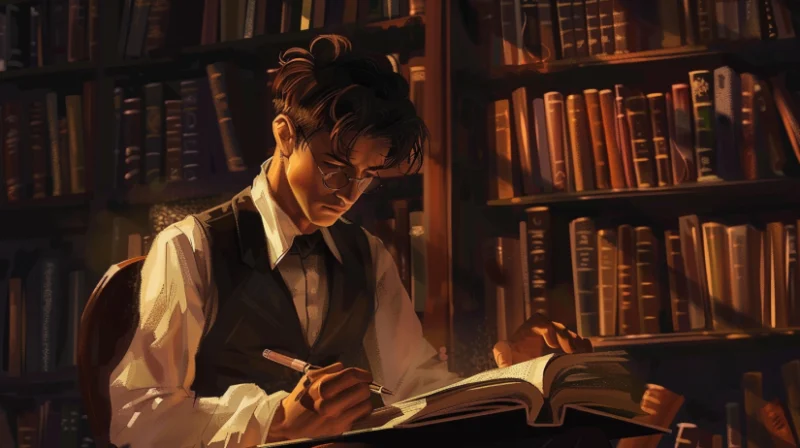
守ったほうがいいこと
まず前提として、同じ系統の参考書は一つに絞りましょう。
例えば、「重要問題集」「標準問題精講」は大体同じレベルの参考書であるため、どちらか1つを完璧にすることに注力しましょう。
重複している勉強時間を他のことに充てるほうが断然効果的です。
そして、復習をすることに時間をかけましょう。
「一度やった系統の問題は何が何でも正解する。」
これができれば、どこの大学でも受かります。

高3の夏休みまでに使っていた参考書(基礎、標準)
ここからは、物理の参考書ルートを徹底解説していきます!!
まずは、基礎期です。
正直、受験で最も大切なのは基礎力ですので、着実に基礎を固めていきましょう!!
ちなみに僕が予習を一通り終えたのは高3の10月くらいでした。(高分子まで)
正直かなり遅めだと思います。
周りの難関大志望でできる人は8月くらいにはおわっている人が多いです。

化学は理論の平衡以外は割と理解しやすいから、予習をバンバン進めていくとあとが楽だよ!!
セミナー化学・化学基礎
セミナー化学は学校で配布される問題集です。
教科書レベルから中堅大学レベル(総合問題)まで対応できる問題集です。
問題数はすべて合わせると1000問程度あり、基礎定着にはかなり良かったです。
しかし、発展問題以外かなり簡単なので、復習は間違えた問題+発展問題だけをやっていました。
無機化学と有機化学においては、基本問題は飛ばし飛ばしでやってました。(福間と鎌田の参考書をやっていたため)

自分に必要じゃない問題は飛ばすことも効率を考える上では重要だよ!!

大学受験Doシリーズ
大学受験Doシリーズ :概要
基礎定着や予習をするうえで非常に役に立ったのが「福間の無機化学の講義」と「鎌田の有機化学の講義」です。
「化学って暗記ばかりで面白くない」って思ったことはありませんか??
実は、高校化学は本質(電子の移動)さえわかってしまえば、暗記すべき量を格段に減らすことができます!
「高校化学の本質を知る」にはもってこいの本です!!
大学受験Doシリーズの良いところは以下の通りです。
・電子の関係を重視した本質的な説明がされている
・無駄がなく、網羅性がある
・初学者の時から、入試本番まで使える
・わかりやすい説明でつまずくことがない
・演習問題がかなりあるので力がつく
大学受験Doシリーズはその章の概要を読んで、そこに付随している練習問題をやって理解し、最後は演習問題をやるという、すべてを兼ね備えるものです。
流石「講義」というまであります。
この本は学校ではあまり教えてくれない、化学反応はすべて電子が関係するということに基づいて議論が進みます。
これは非常に役に立つ考え方で、「無機化学も理論化学」と駿台の先生が言っていましたが、そのわけが理解できます。
また「演習問題もついていて、初学者レベルから中堅大学標準レベルまでに対応しており、無駄がなく網羅性があり、なおかつ初学者にわかりやすい」というまさに良書の鏡です。
別冊で赤シートで覚える用語集も入っているので本当に重宝しました。
※理論化学はスタディサプリでやったため、大学受験Doシリーズは買いませんでした。

大学受験Doシリーズ :やり方
やり方は至ってシンプルで、そのまま順番通りに進めていくだけです。
もちろん間違えたものや理解できないことはわかるまで復習しましょう。
そして、隙間時間を利用して、別冊の用語集をすべて覚えます。

有機化学の用語は、問題を通して覚える感じのほうがいいよ。
一気に覚えようとすると、嫌になるから。

スタディサプリ
スタディサプリ:概要
僕は高校二年生から受験を意識し始め、高二の初夏くらいから、スタディサプリの理論化学をやり始めました。(坂田先生)

スタディサプリは現在(2023年8月)、月1815円(一年契約の場合)で大学受験の講座が受け放題となっています。
通常のリーズナブルな塾が週一、一教科で15000円であることを考えると、一教科をスタディサプリで受けるだけでも、約8分の1の値段となり破格すぎる値段です!
僕は化学と英語をスタディサプリでやっていましたが、英語は関正生先生、化学は坂田薫先生でどちらも超一流の先生です。
坂田先生は現在駿台化学科の先生でもあるので、駿台と同じレベルの授業が月1815円で聴けるのです。
Youtubeにサンプル動画があるので、ぜひチェックしてみてください
スタディサプリ・化学のいいところ
・いつでも、自分のペースで、どこからでも授業を受けられる
・板書がきれいかつ説明が超絶わかりやすい。
・声が明るく、楽しそうに授業をする
・とにかく値段が安いのに、神授業を受けられる
予備校に何十万と払う前に、まずはスタディサプリを使ってから決めないと、絶対に後悔します。
坂田先生は神レベルの先生です。
授業のテンポがいいのに、超絶わかりやすい。
現象の背景も体系的で丁寧な説明でしっかりわかる。
そして、明るくて、楽しそうで、板書がきれいで、かわいい。
悪いところは「自分を律してやらないといけないところ」くらいです。

スタディサプリ:やり方
・高3の講座をやる
・やりたい講座を決めて、授業予定を計画する
・絶対に問題を解いてから講義を聞く
・教科書は用意する(メモもしっかり取る)
・復習を絶対にする
まず気を付けてほしいのは、高2であっても高3の講座をとるということです。
スタディサプリは高3の講座だけが大学受験用となっています。
まずは、スタンダードレベルから始めましょう。
正直ハイレベル講座(難関大用)は時間があったらでいいと思います。
ハイレベル講座をやるんだったら、その前に後で紹介する標問をやることをお勧めします。
スタディサプリは隙間時間にできることをうたっていますが、タブレットなどの大きい画面で、教科書を印刷し用意(売っているやつでもいい)して、メモしながら授業を受けるという方が何倍も勉強効率がいいです。
そして、何度も言いますが復習は絶対してください。
予備校選び初心者の方は、「とりあえずスタディサプリからやってみる」ことをしないと損をすることになるでしょう。
「スタディサプリ大学受験講座の口コミ:辛口レビューと失敗しない使い方まで(活用歴2年)」にてスタディサプリの詳しい講評をしています。

化学の新研究
「これはこういうものだから、どうしてとか言わない!」っていうことが結構ありますよね。
でも、何でなのかがわからないとモヤモヤするのが人間です。
そんな、「論理的に理解したいんや!!」と思っている人に「化学の新研究」をおすすめします!!
例えば平衡定数がなぜあの式になるのか、分子の形がどうやって決まるのかは、「おぼえろ」と言われますが、化学の新研究を読めば論理的に理解できます!
高校の授業で教わらない詳しい背景を知るには「もってこいの本」です。
そして化学の本質を知ることができます。
正直辞書のようなもので見た目も中身もごついです。
受験化学の力が直接つくわけではないので、嗜好品として楽しんでいければベストです。
読んでいるだけで、化学の奥がわかるので化学の暗記が耐えられない人には必見の一冊です。

「化学の新研究」は高2から持っていたよ。
理論化学を習ううえで理解を深めるのにかなり役に立ったよ。
あと読んでいるだけで、面白い!!

高校3年の夏休み明けから使っていた参考書(発展)
続いては、受験後期です。
僕は、9月から化学の標準問題精講をやり始めました。
過去問は9月の後半あたりからスタートしました。
正直、僕の周りの難関大志望の人は夏休みから過去問を始めていて、「これは遅れたスタートを切ることになるな~。大丈夫かなぁ~。」と思っていましたが、この時期でちょうどよかったです。
むしろ、基礎が固まっていないのに過去問をやるのは、無謀すぎて勉強の意味がなくなってしまうので、慎重にいきましょう。
※第一志望の問題の難しさと傾向を把握するのは高3春までにやっておいた方がいいです。
冠模試や過去問を1回分はやっておくようにしましょう。
では、後半の参考書ルートです。
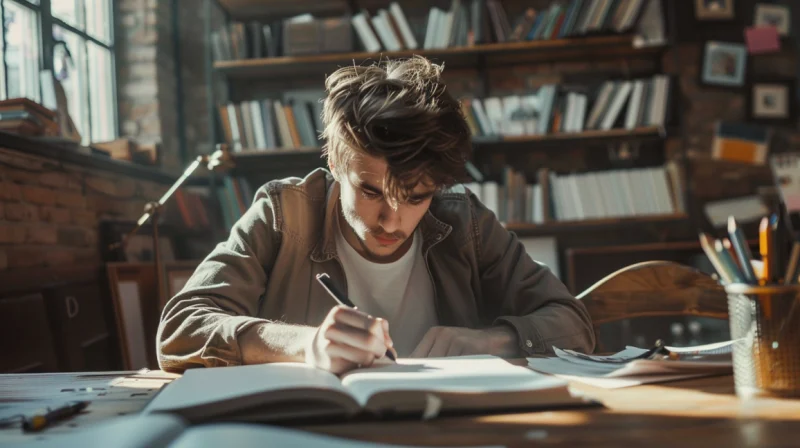
標準問題精講
標準問題精講:概要
「化学は範囲が広すぎるから、精選された良問だけを解きたい!」と思っている人は「標準問題精講」をおすすめします!
「標準問題精講」は過去問との架け橋となる問題集です。
この問題集のレベルは、難関大(旧帝大、東工大、早慶、医学部)標準問題レベルです。
重要問題集の少し上のレベルの参考書です。
セミナー化学とは少しレベルが離れています。
標準問題精講の良いところは以下の通りです。
・問題数が少なくて、一周に時間がかからない
・解説が丁寧で分かりやすい
・考え方を体系的に示してくれる
・良問ぞろいで無駄がない
まず、全問題数が100問程度と問題の数はかなり少ないです。
その代わり解説が非常にわかりやすく、難しい問題を体系的に学ぶことができます。
難易度は巷でいわれるほど難しくはないです。
東工大化学の架け橋としては最適なレベルだと思います。
実際東工大化学はここ10年程度は易しいので、これ以上難しい化学の問題集はオーバーワークです。
※化学満点を狙っている人はもっと上のレベルの参考書を買ったほうがいいかもしれません。

標準問題精講:やり方
・やる順番は適当
・まずは実践的に時間を測って解く
・20分くらい経過して手も足も出ないようなら解答を見る
・それ以外は頑張れるまで頑張る
・答えを見てしまったときは悔しがる
・復習を絶対にする(間違えた問題は絶対)(2周はしたい)
一番大切にしたいのは、考えること。
考えて、考えて、考えつくして、それでわからなかったら負けを認めて、解答を見て残念がる。
この繰り返しがあなたの力を最大限まで高めるシンプルでかつ、最も効果的なやり方です。
たまに、すぐ解答を見るよう勧めている人もいますが、何を考えているのかよくわかりません。
それでは、考える力や思考力が養われません。
解法暗記だけやるのは一番頭の悪い勉強の仕方だと僕は思っています。
この問題集は試験のように実践的に使うのが一番良いやり方だと思います。

過去問・予想問題
過去問は、東工大は青本、その他は赤本で用意していました。
過去問・予想問題についてはこちらの記事で解説しています↓↓
番外編
Youtube勉強
僕は受験期に毎日Youtubeで問題を解いたり、勉強に関する面白い話を聞いたりしていました。
化学に関しては、予備ノリの無機化学の色の授業は絶対に受けたほうがいいです。
この授業をメモして覚えるだけで、無機化学の色は敵なしになりました
Youtube勉強法については過去に出したこちらの記事をご覧ください。

駿台:化学特講
僕は冬に、駿台の化学の難関大向け講座を受けました。
内容はハイレベルで、講師は中村雅彦先生でした。
とても授業に熱のある先生で、難問も体系的に解説し、時にマニアックな化学の雑談もしてくれるという素晴らしい先生でした。
直前講習
駿台では直前期(共通テストが終わってから)に直前期講習があります。
化学では東工大プレという、試験をした後解説をする形式の講座をとりました。
直前期にかなりの緊張感を味わえたのでいい経験になりました。
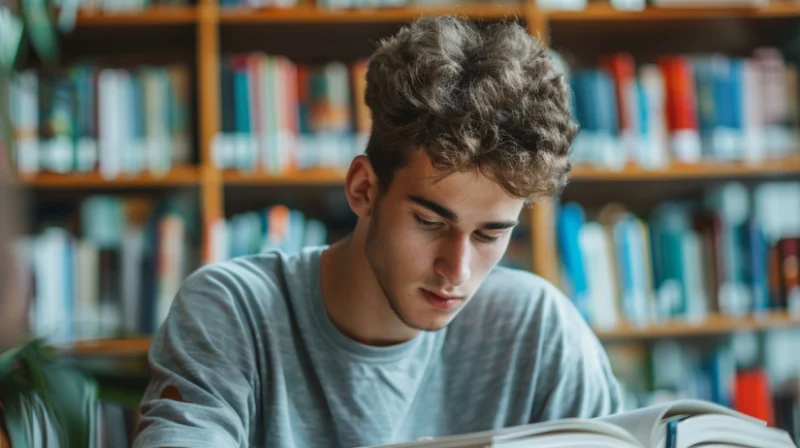
共通テスト
一応、東工大も足切りが存在し、私立の共通テスト利用も狙っていたので、共通テストも僕は割とやりました。
僕は共通テストのような、短時間でたくさんの問題をやることが苦手で、結局あまり伸びなかったですね。

共通テストは、努力に見合うような結果は出なかったね。
人には向き不向きがあるからね…
まとめ
僕の東工大合格へグッと近づけた化学の参考書
・大学受験Doシリーズ
・スタディサプリ
・標準問題精講
・化学の新研究
この4つは使い方次第で、入試攻略において圧倒的な武器となります!!
何度も言いますが大切なのは、自分で決めた参考書を一冊完璧にすること。
そして復習を必ずすること。
応援しています!!!




今日も最高な一日にしていこう!!
See you soon!!


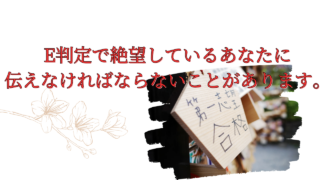






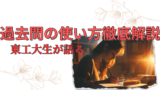



コメント